「DeepSeekショック到来!米テック株は大丈夫?」投資法とPERで徹底分析

DeepSeekの登場と直近の動向
ここ最近、AI分野の話題の中心となっているのが「DeepSeek」。
「安価に高性能なAIモデルを開発できる」と突如クローズアップされ、NVIDIA(エヌビディア)をはじめとする半導体銘柄や、それらを支える電力株にまで大きな影響を与えています。従来は「最先端のAIを動かすには高価なGPUをたくさん導入しなければならない」という認識でしたが、DeepSeekの技術が「そこを大幅に軽量化し、必要リソースを減らせる可能性がある」との見方が一気に広がったのです。
■主な証券会社の比較表
予想外の株価急落とリバウンド
- 初動:パニック的な売り
DeepSeekが報じられた直後、「高価なGPUの需要が減るのでは」「データセンターの電力需要増加がそれほど見込めなくなるのでは」という懸念が急浮上しました。結果として、大型テックや電力セクターの一部銘柄が大幅に売り込まれる事態に。 - 翌日以降:落ち着きを取り戻す
しかし、その後は売りすぎと判断した投資家の買い戻しが入り、エヌビディアなどは大きくリバウンド。また「安価なモデルが普及すればAIの裾野が広がり、むしろ関連インフラへの需要は伸びる」という意見も出始め、短期的なパニックは和らぎつつあります。
著名アナリストや企業トップの声
- Wedbushのアナリスト
「DeepSeekが米国の確立された技術インフラに一気に対抗できるかは疑問が残る」「現状、NVIDIAはAIインフラを牽引するリーダーであり続けるだろう」というレポートを出しました。急落後のエヌビディア株が再び買われたのは、このようなリーダー評価の再確認が大きかったとも言えます。 - OpenAI CEO サム・アルトマン
DeepSeekの低コスト・高性能モデルについて「価格に見合った非常に印象的なモデルだが、OpenAIとしてはより優れたモデルを準備している。近々いくつかリリースがあるだろう」とコメント。安価な対抗馬の登場は、「さらに高度なモデルを投入する原動力にもなる」という前向きな捉え方をしています。 - Microsoft CEO サティア・ナデラ
「DeepSeekの登場はAI開発のエコシステム全体を押し上げる可能性がある。計算資源が割安になれば、その分新たな活用方法が生まれる」と楽観的な見方。大手クラウド事業者としては、より幅広い顧客がAIを導入する道筋ができると期待しているわけです。 - Appleやメタへの影響
Appleのように独自AI基盤がまだ限定的な企業は、他社のソリューションを取り込みやすくなる可能性があります。一方、メタ社はオープンソース路線を突き進んでおり、「小型化されたモデルをいち早く取り入れられる」という強みをアピール。今後、様々な企業が独自の付加価値やシェア獲得競争を繰り広げそうです。
本当に電力需要は減るのか?
- ジェフリーズや一部アナリストの見方
AI分野の拡大はデータセンターの電力消費を大きく押し上げると予測されてきました。しかしDeepSeekの省エネぶりが本物なら、「当初見込まれていたほどの電力需要は生じないかも」との指摘があります。これによって、原子力発電などの設備投資や大規模電力プロジェクトへの期待が一部で後退している面も。 - 裏腹に拡がる裾野
一方で「AIがより安価に作れるなら、それだけ多くのプレイヤーがAIを取り入れるようになるはず。導入者の数が増えれば、結果的にはトータルの電力需要も伸びていく」という意見も根強いです。小さな企業や個人事業主が続々とAIを導入するなら、限界効用が一気に広がるかもしれません。
総じて、DeepSeekショックは「より低コスト・高性能のAIが普及することで、市場全体の裾野を拡げる大きなきっかけになりそう」というプラス要因が見えてきました。短期的には「NVIDIAなどへの逆風では?」と不安が募りましたが、大手アナリストやトップ企業経営陣の声を総合すると、AI市場が一層拡大していく可能性も十分にある、という見方が強まっています。
グロースとバリュー、そして市場のサイクル
DeepSeekショックのようなサプライズが起きたとき、私が注目するのはグロース株とバリュー株の資金循環です。昨今は金利やマクロ経済の先行きが読みづらいだけに、「グロース優位」「バリュー優位」の流れが短いスパンで変わりやすい状況といえるでしょう。
- グロース株優位のシナリオ
「金利が下がるほど割引率が低下し、将来成長分を織り込みやすくなる」という理屈は定番。一方で、それだけでは説明できないほどAIなど新技術関連のテーマが強いと、グロース株は金利動向に関わらず買われ続ける局面もあります。 - バリュー株優位のシナリオ
金利上昇局面や、グロースに資金が集まりすぎてバリエーションが極端に高まると「割安感のあるバリュー株に鞍替えしたい」という投資家が増えます。こうした循環が起こりやすいからこそ、どちらのスタイルもフラットな目線でチェックする姿勢が必要だと考えています。
PERを使った銘柄選び:数値だけでなく“変化”に注目
DeepSeekのようなニュースは、個別銘柄にも大きく影響します。特にAI関連などグロース性の高い銘柄の場合、PER(株価収益率)が一見「割高」に見えがち。しかし私は、PERだけを鵜呑みにせず“非連続的な伸び”に着目するようにしています。
- PERはあくまで目安
PERが低い=「割安」とは限りません。急成長中のベンチャーや進行株は「今までは赤字でも、来期以降急に黒字転換&大幅成長する可能性」があるからです。表面的なPERでは見切れない潜在力に注視します。 - 非連続的な変化を見極める
たとえば四半期ごとに前年同期比で大きく利益を伸ばし、さらに急に50%超の伸びが出たような銘柄は要チェック。「何らかのブレークスルーが起きている」可能性があるからです。 - 経営姿勢やIRへの注目
特に中小型株の場合、経営陣の考え方やIR資料の充実度も重要。リソースが限られた段階でどこに注力しているかが、将来の株価を左右します。AIのように技術競争が激しい分野では、社長やCTOの方針・姿勢にも明確な差が出やすいと思います。
トップダウンとボトムアップのハイブリッド思考
AI市場が大きく揺れる中、私が意識しているのが**“トップダウン”と“ボトムアップ”を組み合わせる(ハイブリッド)アプローチ**です。
- トップダウンアプローチ
まずマクロ要因や金利動向、米国市場(FOMCなど)のシグナルを確認して、「資金がバリューに向かいそうか、グロースに向かいそうか」を大まかに見極めます。 - ボトムアップアプローチ
さらに決算資料を読み込み、経営陣へのヒアリングやIRイベントをチェックして、非連続的な成長の兆しがある銘柄を拾っていく。たとえば、予想を大きく上回る業績を連続して出している場合や、新製品が爆発的に受けているケースなどを特に重視します。
こうすることで「安いか高いか(バリエーション)」「成長率は本物か(ファンダメンタルズ)」の両面から銘柄を探すことが可能です。
まとめ
DeepSeekショックから分かるように、AI市場は常にサプライズが起こり得る領域です。NVIDIAや電力関連銘柄の急落を見て「AIバブルの終わりか?」と思ったら、翌日にはリバウンドするほど、不確実性もボラティリティも高い。大事なのは短期的な乱高下に流されず、投資を続けられるスタンスで臨むことだと思います。
- 長期視点の成長期待
AIはまだ始まったばかり。安価なモデルが普及すれば「導入する企業・個人が増える → 結果的に市場規模がさらに拡大する」という好循環も見込めます。 - 冷静な判断で撤退しない
一時的な下落にパニックを起こすと、せっかくのチャンスを逃しかねません。投資をやめず、「自分なりの基準で“買い”を判断できるライン」だけは常に持ち続ける。
DeepSeekのような技術革新は、むしろ大手テックや関連インフラ企業の成長余地を広げる引き金になるかもしれません。リスクを十分意識しつつも、「グロースとバリューのどちらにも目を光らせる柔軟さ」と「PERをはじめとした定量面&非連続的成長を見極める目」を大切に、今後のAI相場を楽しんでいきたいですね。


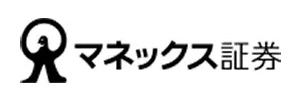
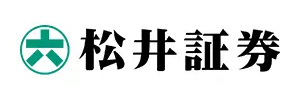
コメント